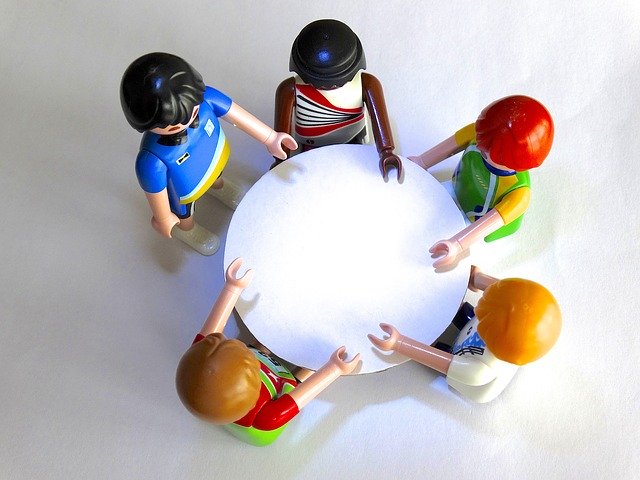介護士の仕事は、ご利用者様のお世話だけでなく、記録や送迎、応接対応、備品管理など業務は多岐に渡り、毎日時間に追われる状態になりがちです。そして、役職が上がるとマネジメントや研修や会議、地域連携などさらに多忙になっていきます。
本当は、
利用者様ともっと話せる時間を作りたい。
職員にちゃんと向き合い仕事を教える時間を作りたい。
落ち着いて事務が出来る時間を作りたい・・・など。
と考える介護士さんも結構多いのではないでしょうか?
そんな方向けに介護施設の管理者をしていた私の経験をふまえ、効率よく業務を回すポイントをご紹介します!
時間の無駄をなくせば出来る
まずは、当たり前な事でもあるのですが、業務中時間を無駄にしている事はないでしょうか?
無駄になりがちな事を大きく分けると、
・やる必要のない業務(やっても効果が薄い業務)
・業務以外の無駄な行動
があります。
前者は組織上のルールもあり中々変更が難しいケースもあると思いますが、後者の時間は個人の努力で減らす事は可能です。
普段仕事してて、ついやってしまっていることはないでしょうか?
まずは業務以外の無駄な行動はないか、見直してみましょう!
例えば、職員間のおしゃべりです。
チームで事業所運営をしているので、仕事以外の事も含めコミュニケーションをお互いに取り合う事は重要です。仲の良い同僚がいるから頑張れるという方もいるでしょう。
しかし、必要以上の長話ややり取りは時間がもったいないです。
例えば、事業所の職員3名で勤務中15分おしゃべりをしたとしましょう。
時間を換算すると、15分×3名=45分 の業務時間を無駄にしてしまった事になります。つまり、45分の労働力を無駄にして、価値を生産する機会を損失させてしまった事になります。
もう少し具体的に言うと、
45分あったら、利用者1名〜2名の入浴は少なくとも終わるくらいの時間ですよね。
って事です。
もっとやれる事があるはずです。
マルチタスクで仕事を抱え込むのはキツイ
介護職に求められる業務は非常に多岐に渡り、かつ同時並行で処理していかなくてはいけない場合も多く大変なところです。
業務が多岐に渡ってしまうのも人手不足が原因にあると思いますが、現場はそれでも回さなくちゃいけないですよね。
中には重度の認知症の方の対応をしながら、業務で手を動かし続けるなど右脳と左脳をフル回転せざるを得ない事もあったりもする方もいるのではないでしょうか。
しかし、こうしたマルチタスク型の体制は、一つ一つのパフォーマンスが悪くなる可能性が高いです。
2009年米国科学アカデミー紀要で公開されたスタンフォード大学の研究「メディアマルチタスク作業者の認知的統制」では、重度のマルチタスクでの業務は注意力が個々に分散することから、個々に生産性が低下してしまう。
https://www.infoq.com/jp/news/2009/09/study-multitasking-performance
というデータもあります。
シングルタスクの作業に近づけよう
一般的に男性より女性の方がマルチタスクでの作業が得意な方が多いようです。
主婦経験のある方なら朝は料理と洗濯をしながら子供と会話するなんて事が普通に行っていたりします。しかし、仕事全体の生産性を考えるとマルチタスクでの作業は生産性が長続きしません。
では、どうするか?
出来るだけシングルタスク型近づける事です。
パワーを集中して投下できる状態にしていく事です。
シングル作業に近づける具体的な方法としては、
①専門性を作り、役割分担をする。
➡︎職員の長所や経験豊富な事、やりたい事、出来そうな事を割り振る事でモチベーションを高くして集中して取り組んでもらう。結果効率よく業務が回る。
②複数同時に業務を行ってもらう場合は担当する領域を近い領域にする。
➡︎仕事内容の近いもの、作業する空間上近いものは意識が分散しにくく業務をこなしやすい。
③やらなくていい事はやらない。
➡︎様々なタスクを複数抱えている場合は無理に同時並行せず、まず「本当にこれやる必要あるのか?」一度考えた方がいいです。やった方がいいかもとやる必要がある事は別物です。やった方がいい気がするけど、効果が実証できていない事はやらなくていい事だったりします。
また、短所になっている事を捨てるのも重要です。
④流れの無駄をなくす仕組みを作る。
➡︎誰が何をいつするのかのスケジュール管理、業務上の連携のルール化する。例えば入浴介助のように、人によって丁寧さやスピードに差が出る業務は、流れのポイントを共有して、ルール化してた方が良いです。
また、業務が潤滑に行えるよう、備品を行う業務の近くに置いたり、職員の動線上やりやすい環境をつくる事も大切です。
入浴や排泄介助、レクリエーション、情報共有、書類作成など場面ごとに考えると改善出来そうなところが、どこか出てくるはずです。
これにより、
- 一人の職員のオーバーワークが減る
- 無駄な動きが減り、残業する職員が減る
- 本当に必要な事にパワーと時間が割けるようになる
という状態になっていきます。
まとめ
介護の仕事で時間短縮をしようと考えると、利用者の介助まで短縮しようとしてしまいがちです。
しかし、自立している方や一部介助で出来る方まで全介助で対応してしまうのは本人の能力を奪ってしまうことにもなります。
中長期的に見ると、こうした全介助を続けた場合は能力の低下によって介護負担が増える可能性も高いですし、そもそもケアプランで目標としてるケアが対応出来ていない事にも繋がります。
多少時間がかかっても自立支援の介護続ければ、ご本人の能力が維持されたり、家族や職員の介護負担が軽くなる可能性が出てきます。
これらの点から、まずは職員の業務から見直すことが大事です。
業務は素早くこなし、利用者の対応はペースに合わせられる。
そんな介護職の多い現場はサービスの質も良い事業所にもなっていきます。
今回は、時間がない介護職の現場をスムーズに回すには?というテーマでした。
読んでいただきありがとうございます。