SNSの利用が世界的に当たり前になっている中で、
不適切投稿や誹謗中傷などの問題も起きています。
そうした側面のリスクをふまえ介護サービス事業所でも、個人のSNS上での発信や投稿を制限している会社も少なくありません。
「やりたい!」
と思っていても会社はやってほしくない!っていう。
それはなぜなのか?
その理由を解説しています。
SNSを会社的にはあんまり使って欲しくない理由

職員さんがコミュニケーションの一環で同じ趣味の人同士で交流したり、社会問題を議論したりなどに利用するのであれば、それほど問題にはならないと思います。
ですが、事業所の職員としてイメージを損なうような使い方は、
会社からするとマジやめて!
という気持ちになってしまうものです。
たとえば、
・職員による不適切な投稿(業務中の問題行動、イメージを損なう写真や動画など)
・SNS内での攻撃的な発信、それを同調するような投稿
・特定の思想や内容(嫌悪感を示す人も多いような内容など)の投稿
・プライバシーや著作権の侵害に関係する投稿
・オープンにして欲しくない内部の事情、営業秘密の漏洩
など
法的に会社として責任を取らなきゃいけないケースもありますし、
会社としては、
いつそのようなことが起こるか分からないリスクは出来るだけ抱えたくない。
介護サービスは、なんと言っても利用者さんありきのサービス。
利用者の立場になって理由もなく不快な気分にさせてしまうのは御法度。
自分のプライバシーが知らぬ間にSNSなどで拡散されることを嫌がる人は、
今の若い世代と比べて多いですし、自分が利用している介護施設の職員がクレイジーな投稿をしていたら、
サービスを利用するのもイヤになってしまうかもしれません。
個人情報の外部流出の問題は介護サービスだけでなく、社会的に重要視されている問題でもあるので、
SNSなどで働いている職員から流出するリスクができる限り抑えたいのが、会社の方の心情としてあります。
事業を継続するための、リスク回避策とも言えます。
また、SNSは情報の拡散力があります。それゆえバズってしまったら、多大な影響を関係者に及ぼします。
ちょっとした問題がどんどん広がって大きくなってしまう怖さもあるんです。
悪い情報がSNSでバズってしまったらどうなる?
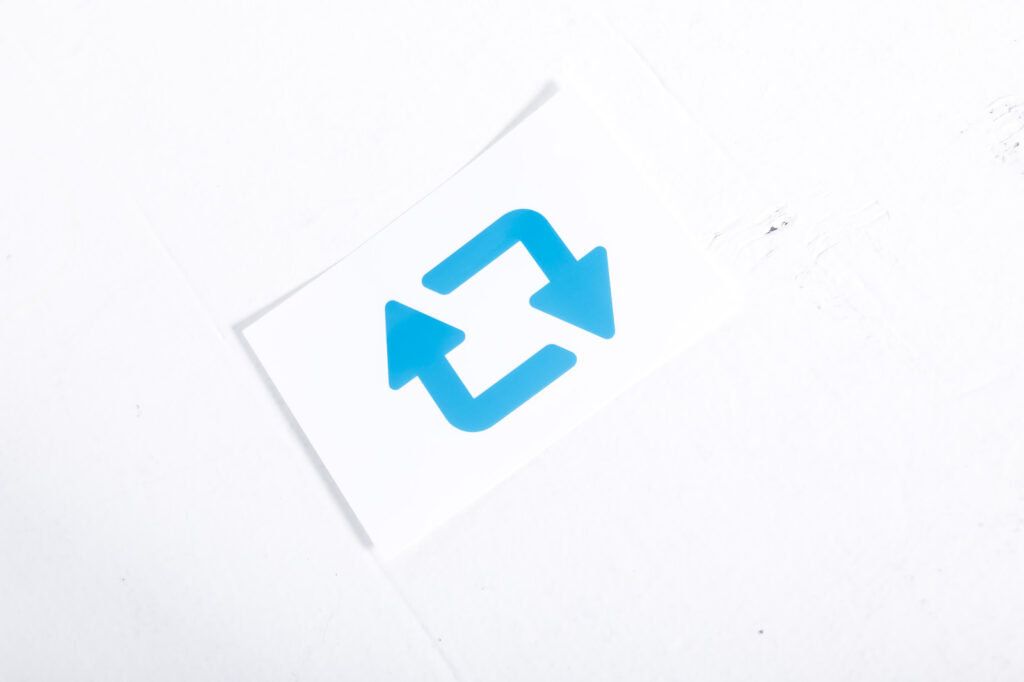
もし、職員がSNSを利用していて、
悪い情報や投稿が世に出て広がってしまったら会社にどんな影響が出てくるのでしょうか?
ざっと考えてみると、
・本人との事情や事実確認、削除依頼などの話し合い
・利用者、利用者家族、協力事業所など関係者への説明と謝罪
・職員への説明、対応依頼
・イメージ低下、信用低下による利用者減少→収益減少
・職員への誹謗中傷、職員の退職に繋がる可能性
・示談や裁判などの法的手続きや処置
・再発防止策の検討、内部マニュアルや就業規則などの見直し
・新規立ち上げ中の場合、申請拒否となる可能性
うーーーーむ。
・・だいぶ大変ですね!・・・・・任されたらやりたくない笑
普段の業務と並行してこうしたことに対処しなくてはいけなくなるわけですし、
せっかくそれまで職員みんなで頑張って作りあげてきたサービスのイメージを損なうことになるのは、
何より辛い!!!
こわいっ!!!!!
事業所側で制限したくなるのも当然ですよね。
SNSをやっていない職員にも迷惑がかかるし、
結局対応することになるのはリーダー職員や各部門の職員になるでしょう。
働くメンバーに負担が大きくふりかかるリスクが起きる可能性があります。
そこまでしてやる意味あんの?
と思っても不思議ではありません。
そもそも会社が介護職のSNSを制限できる権利はあるのか?

会社が介護職にSNSの制限をかけるには法的な根拠も必要だけど、
果たして制限できる根拠はあるんだろうか?
ちょっと調べてみました。
インターネット上で弁護士や社労士など法律の専門家の方が書かれている記事などを確認すると、
SNSを全面的に禁止を要求してしまうというのは会社側に違法性が高くなってしまうようです。
理由は、
全面的な禁止は、業務内ならまだしも、業務外の時間までも禁止してしまうことになるから。
労働に関する法律に触れてしまい、企業のイメージを損なう恐れがない一般的なSNSの利用をしている職員さんからは請求されてもおかしくない状況にもなり得るようです。
とはいえ、会社側もSNSによるリスク対策が出来ないわけではなく、
業務内は当然として、業務外でも、
・仕事上の営業秘密や内部秘密の情報漏洩
・会社と個人の意見を一緒に混同されかねない意見の投稿
・内部の個人情報の漏洩
・イメージ低下や業績低下に繋がる画像や音声、動画の投稿
など
は合理的な制限であるとして、業務命令としてルール化することは可能なようです。
こちらのサイトが参考になります。(”社員個人のSNSアカウントを、会社が監視、利用禁止できる?” 企業法務弁護士BIZ)
SNSの利用の仕方を制限するにあたって、合理性があるかどうかはポイントのようですね。
とは言え後出しのルールでは揉めてしまう可能性もあります。
秘密保持誓約書や就業規則などで、
SNSの投稿を制限する内容を定めているところもよくあるのは
事前に同意してもらった上で働いてもらえるようにする為
でもあります。
SNSを制限することで見落とすことになるものはないか?
ここまでSNSのリスクについて説明してきましたが、
デジタル化が進んでいる中、多くの人がやっているSNSを制限することは会社にとっても損失はないのでしょうか?
その点についてはこちらの記事で解説しています。
SNSを利用したい介護職はどうすればいいのか?

SNSをやりたい人はやっても大丈夫です。
アカウントを持つこと自体を禁止する法的な根拠はないからです。
ただし、会社の許可や投稿を認められる立場にいないのであれば、個人の見解と会社に属している介護職としての見解は別物として利用したほうが良いでしょう。
もし誤って投稿してしまった場合は早めに削除したり、訂正や謝罪の説明も場合によっては必要です。
また、個人での利用だけではなく、会社のPR担当などになって法人アカウントを業務の一環で利用するという方法も取れるでしょう。
とは言え、いくら制限があろうが、実際は隠れてみんなやっていたりもするのがSNSだったりします。
普通に使っていれば友人と繋がったり、交流の幅が広がる良いツールです。
社会人としての常識も考え、投稿する前に一考する時間が何気に大事かもしれません。
今回の記事は以上となります。
読んでいただきありがとうございました。
もし記事が良かったら、
各SNSのいいねやシェア、はてなブックマークなど宜しくお願い致します。




コメント