どうも、なおべい(@naobei)といいます!
今回は、尾原和啓さんの「プロセスエコノミー」という本を読んで、
介護事業所のPR活動に今後生かせそうだなと思うところがあったのでアウトプットします。
サービスとして求められるケアはどこもやっている
みなさんは良いケアと聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
「利用者本意のケアが出来ている」
「しっかりとした環境が整っている」
「職員が要介護者に対応できる技術を持っている」
などが浮かんだりするんじゃないでしょうか。
こうした部分のサービスレベルのみを考えたら上はおそらくキリがない思います。
優秀な介護職だったり、丁寧に時間をかけたり、多くの人が関わったりすることが出来ればよりその人に合った介護のサービスを提供できる確率は上がっていきます。
一方、介護サービスとして「普通にやっている」というレベルを考えてみると、
十分その地域で助かっているサービスにしっかりなっているはずです。
むしろサービスが悪い事業所を見つける方が難しい。
介護保険制度の施行から20年以上経過し、かつてあった劣悪なサービス事業所は廃止や改善してますし、今残っている事業所や新たに開設している事業所は、行政が提示する一定の基準をクリアした事業所になっています。
また、現在はインターネットからSNSなどでの評判、地域のケアマネージャーらの口コミ評価など
でも広がってしまうこともあるので「ちゃんとやっていなきゃ」残れません。
ざっくり
・デイサービスなら、送迎・入浴・交流。
・訪問ヘルパーなら、家に行って介助や生活支援。
・ケアマネジャーなら、プラン作成や相談支援。
など、サービスとして求められている基準の内容は、基本的にどこもちゃんとやっていると思います。
「今日は、職員のモチベーションが低くて、入浴対応出来ませんでした。」
みたいな事業所は99.99・・・%くらいあり得ないはず。
できなかったらサービスを使う意味自体がなくなってくる。
どこで差別化をはかるか?

では、どこもケアをちゃんとやっているとすれば、
どこで差がつくのか?
前述した、
「利用者本意のケアが出来ている」
「しっかりとした環境が整っている」
「職員が要介護者に対応できる技術を持っている」
サービスの部分はもちろん差がつきます。
介護サービスの売り物はまさにこの部分でもあるからです。
そしてサービスレベルについては上限のない世界。
持っているところが勝つ世界です。
つまり、
・より幅広く多様なニーズに対応できる優秀な人材や資源を持っている
・環境設備に投資できる資金力を持っている
・時間をかけられる余裕を持っている
などサービスレベルを上げる付加価値を創出する力を持っているか。
とはいえ、どの介護事業所もこの世界線で競争しているわけですが、
ここだけで戦うのは、
「そんなに色々持っていない」
「人員不足で追いついていない」
事業所には結構厳しいですよね。
うーーん、ケアの差別化競争を抜けてどうにかならないものか。
用途以外の意味にも価値がある
そこで一つのアイデアとして、
「プロセスを価値にすること」です。
介護サービスを作っていく、良くしていこうとする過程となるストーリーが新たな価値にもなるんです。
ブログやSNSでのストーリーの開示については、こちらの記事でも紹介しています。
実際サービスの取捨選択をする時は、
ケアマネさんも利用者さんのニーズに合うサービスをたくさんの事業所から考えて選ぶし、
家族も自分の親のニーズや性格、こだわりまで考えて合うサービスを考えますよね。
そこでは・・・
なぜ、そのサービスが合うか?
を説明できるモノの存在は重要になってきます。
その中に、職員の質、環境設備、体制などを作っていくストーリーも含まれてくるんです。
そして、人間は「動くぞ!」というときは感情で動くことの方が多いそうです。(ダニエル・カーネマン「ファスト・アンド・ロー」より)
例えば
ナイキは、靴の機能性を広告に出すのではなく、「JUST DO IT」と感情に訴えるキャッチコピー出し、そこにストーリー性を加えたPRを全面に出している
合理的にウチの商品良いよ!とアピールするなら、モノの良さ(機能性、価格、品質など)を出すべきですが、その点での競争は熾烈です。
ナイキ、アディダス、プーマ、FILAなど商品レベルの戦いは大きく差があるか微妙ですし、どれが機能面で抜き出てるか考えると難しくなる。
でも、現実「ナイキがいいんだ」という人はいますよね。
ナイキの精神が溜まらなく好きなんだ!!みたいなスポーツ選手も多いですよね。
実際ナイキは業界トップの時価総額3兆円規模の会社です。
他の業界も見てみると、
スマホで言えば、アンドロイドより「iphoneがいいんだ!」という人や、
クルマで言えば、日産より「フェラーリやBMWがいい!」、
バッグで言えば、近所の洋品店より「グッチやヴィトンがいい!」という人はいます。
単純な商品の用途(使えればいい)を超えた意味に価値を見出して、選んでいるワケです。
介護サービスで用途以外の意味をもたせるには?
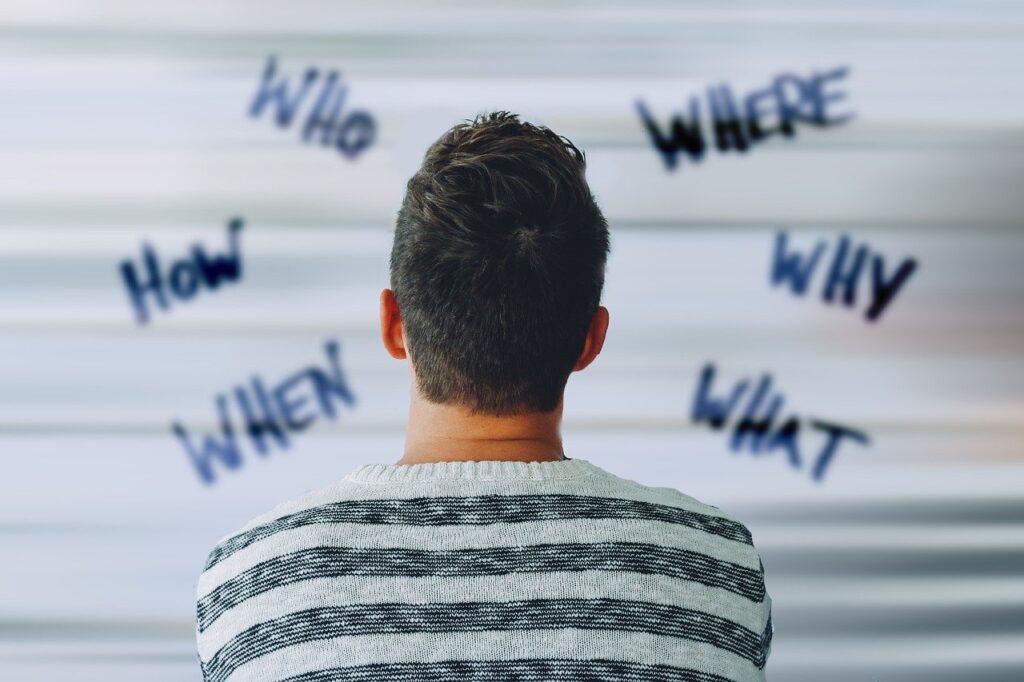
では介護サービスはどうなのか?
介護サービスでもサービスの品質を上げる以外に意味をPRできるところはあります。
考えるべきは、
「なぜ、そこの介護サービスがいいのか?」
創業者、職員、利用者、家族、関係者それぞれ捉え方は違うと思います。
おそらく「ここがいい!」と決めた意味はそれぞれ違うはずです。
たとえば、
創業者なら、「介護の〇〇な部分の問題解決をしたくて・・・」
職員なら、「まだ入ったばかりだけど、自分の意見もちゃんと聞いてくれて・・・」
利用者なら、「あそこのサービスのスタッフは真剣に自分のことを考えてくれて・・・」
「ここがいい!」と決めているものがある。
介護サービスに人が集まる流れをたどると、
それぞれに所属する要因となるストーリー(背景)があり、お互いのこだわりのマッチングがされて、集まりができる
ところが本質的なところです。
ということは、こだわりのマッチするような人に共感されやすいよう様々な切り口でストーリーを開示していくことが、介護サービスには求められるんじゃないでしょうか。
・どうしてそのサービス事業所を作ろうと考えたのか?
・なぜ、たくさん介護の仕事がある中でココを選んだのか?
・どんな思いで今の介護に取り組んでいるのか?
・今目指している目標や夢は何か?
・ここのサービスを選んだ経緯は?決め手はズバリ何?
などは、関わる人からすると興味がわくところ。
別に綺麗事だけを並べる必要はないです。
途中のプロセスで失敗しても、それはそれでドラマになる。(失敗しても挫けず頑張ろうとしてる人をみると、人は応援したくなる心理もある)
例えば事業所のブログ投稿でも、
「単にみんな笑顔で楽しく夏祭りを終えることができました〜〜」よりも、
「新人職員を担当にして何度もすったもんだ議論して、無事良い夏祭りにすることができました〜」
な一面を見れた方が、共感は集まりやすいと思います。
色々大変だったんだけど、頑張ったんだな。
この職員さんには今後も頑張ってほしいな。
など。
こうした感情が後に「この事業所いいな」を決める時に決め手になってきたりもします。
合理じゃなく、感情で人が動くのは正にこの部分。
それぞれのストーリーを大事にすれば、その気持ちに共感する誰かは出てくるので、
ぜひPR活動に生かしてもらえたらと思います。
今回は以上となります。
読んでいただきありがとうございました。
もし良かったら、
各SNSのいいねやシェア、はてなブックマークなど宜しくお願い致します。




コメント